個人と法人の税金面の違い|ブログで創業塾0220


個人と法人の税金面の違い
前回でもお話しましたが、税金についての違いを説明します。
経営者となると、個人の年末調整だけではすみません。
事業者として、決算を行い、確定申告を行う必要があります。
どのような税金があるのかをここでは抑えてきます。
個人事業
まず会計期間は1~12月で、翌年3月15日までに確定申告を行います。
通常の商売であれば、確定申告の時に、1年分の税金を同じく3月15日までに、消費税は4月2日までに納付をする必要があります。※平成29年分の確定申告の場合。納付期限は毎年要確認
中小企業診断士もそうなんですが、報酬をいただく時に、顧客が代わりに源泉所得税を売上から差し引いて先に納付している場合は、払いすぎた税金が還付金として、返ってきます。
所得税・個人住民税は給与天引きでも払っていたものと同じです。
新たに加わるのが個人事業税です。290万円が控除なので、それ以上課税所得、利益が出たら納税が必要になります。
法人(株式会社・合同会社など)
法人は決算月を選べます。3月決算が多いですね。
税理士さんにお願いする場合、特にこだわりがなければ、3月以外の空いている月にすると喜ばれます。
法人の場合は、税引前当期利益に対して、法人税・法人住民税・法人事業税を納付します。ざっくりですが、上記3つを合わせて税引前当期利益の約30%くらいです。※図解の数値が誤りです。
その他の主な税金(共通)
消費税
消費税は簡単に言うと、お客様から預かった消費税から、仕入・経費でこちらが支払った消費税の差額を納付することになっています。
前々年の課税売上高(消費税を預かる売上高。通常は=売上高)が1000万円以上になると、消費税の納付が必要になります。
参照:消費税の納税義務の免除
消費税の納付には簡易課税と原則課税があります。前々年の課税売上高が5000万円以下の場合、これを選択できます。
課税事業者になった時にどちらが有利になるか、わからない場合は税理士さんに相談してみましょう。
参考:消費税の納税はどっちがオトク?!簡易課税と原則課税の違い(外部リンク)
固定資産税
店舗・事務所などを事業用に所有している場合は、固定資産税も経費となります。
償却資産税
土地・建物以外の事業に用いる固定資産。例えば、パソコン・プリンター・厨房機器・看板・建物の内装・工場の機械・テーブル・椅子・陳列ケースなどです。対象資産の合計が150万円以下だと免税です。税率は1.4%です。会計事務所時代にこの税金のことを知りました。おそらく事業をしてみないと、知らない税金です。
印紙税
契約書作成時や、高額な領収書で必要になります。
おわりに
ざっと、個人・法人・共通の税金を見てみました。
納税額が大きくなると、昨年の実績から期中に先に払う中間納付の対象にもなります。
資金ぐり計画にはこの税金の納付も頭に入れておかないといけません。
参考:税のカレンダー(外部リンク)
この分野はやはり税務署か税理士さんに相談すると良いでしょう。
商工会や商工会議所で、無料税理士相談窓口を設けている場合もあります。
次回予告
次回は許認可が必要な主な業種についてです。
次の記事:許認可が必要な主な業種
前の記事:個人事業と法人のメリット・デメリット
最初の記事:はじめに
記事一覧:【記事一覧)修行中でお忙しい独立予定者へ~ブログで創業塾
【月定額で創業サポート】オンラインバーゆうてんかのご案内
<自己紹介>中小企業診断士 岩橋 亮(Twitter名:りょうさん)
1980.11.28生。B型、射手座、左利き 大阪府三島郡島本町育ち。関西大学商学部卒 システムエンジニアで上場企業に就職(千葉・東京)。 自己啓発で中小企業診断士の勉強を開始。資格学校の先生に憧れ中小企業経営に携わるべく 社員20人の税理士法人に転職(京都)。 1度目は足切りに泣き2度目で中小企業診断士合格。経営支援に特化すべく27歳で独立。創業時、廃業の危機を乗り越え軌道に乗り現在14年目 「創業時にお金がかからず、継続的に色々と気軽に相談できる場所があれば」 を具現化しようと 2020.4オンラインバーゆうてんかをオープン

SNSでつながり、マーケティング・中小企業経営・創業を学ぶ
インスタグラム
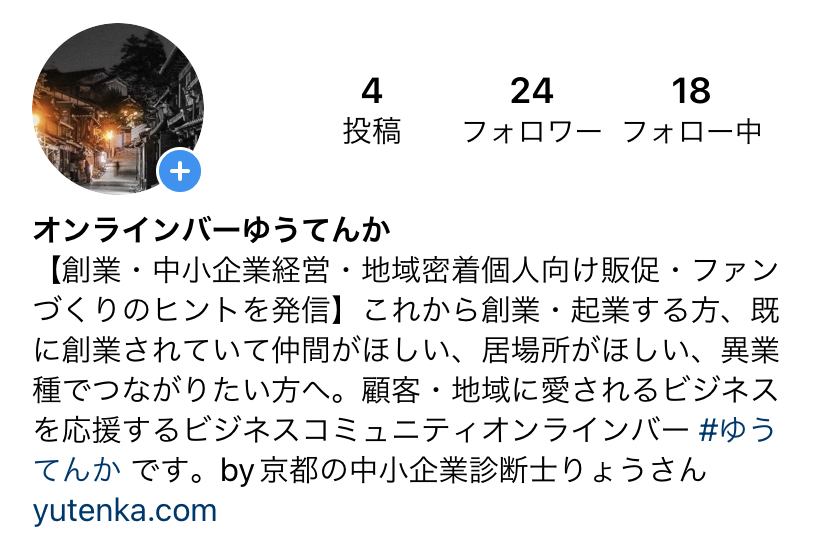
ツイッター






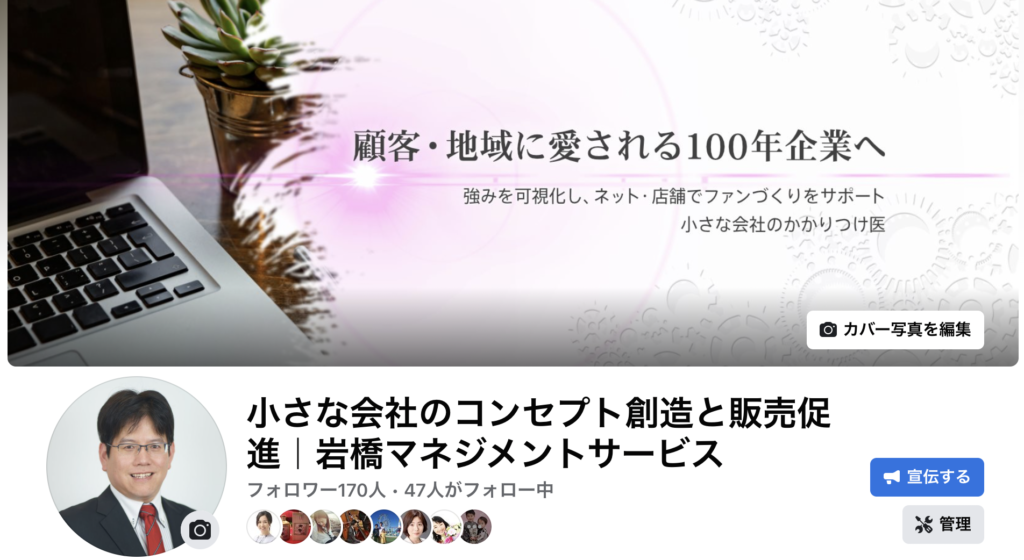
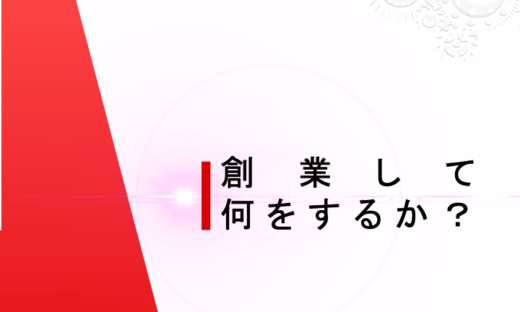
この記事へのコメントはありません。