小さな会社がオリジナル商品を売る方法『売れるネットショップ開業・運営』

【今回のテーマ】
ネットショップの開業・改善
【今回の一冊】
◆タイトル:『売れるネットショップ開業・運営』
◆著者:坂本悟史 川村トモエ
◆出版社:インプレスジャパン
◆ページ数:232ページ
◆2010.5.4
【こんな方にオススメ】(5段階)
●ネットショップをはじめたが、うまく売れない ☆☆☆☆☆
●ネットショップ開業を考えている ☆☆☆☆☆
●ネットショップをしているが、伸び悩んでいる ☆☆☆☆
【レビュー】
●オリジナルブランド商品をいかに売るか
オリジナルブランド商品は徹底的に魅力を伝える
興味を引く実績(有名ホテル納入・地元マスコミ掲載など)、情報開示(製造工程・産地・原料など)
買うべき理由を単なる商品スペック紹介で終わらず、生活の中でどう活きるかまで踏み込んで案内する
売り手自身の自己紹介で信用を高める
<ネットショップの3大施策>
1.集客・・・検索対策・リスティング広告・懸賞・純広告・紹介促進
2.接客・・・コンセプト・店構え・品揃え・看板商品
3.追客・・・メルマガ・同封チラシ・店長ブログなど
<EC4タイプ>
1.有名ブランドタイプ・・・有名ブランド商品・型番商品中心。商品数多い
2.オリジナルタイプ・・・商品数少ない。知名度がなく、開店しただけでは売れない
3.ニッチタイプ・・・ごく限られた客層向け。数少ない潜在客とどうやって出会うか
4.総合タイプ・・・有名商品・無名商品混在。商品数多い。カタログ通販に近い
ネットショップのチェックリスト。
これが本書の印象です。
私が支援させていただいていて、ご縁が多いのはオリジナルタイプやニッチタイプをいかにネットで販売するかが課題の場合です。
本書は楽天出身のECコンサルティング・商品企画を行っておられる筆者によって書かれています。
上記のようにネットショップの3大施策(プロセス)、EC4タイプにネットショップを整理された上で、体系的に1テーマ見開き2ページで解説されています。
事例や写真・図解も多く、補足やコラムも役立ちます。
本書を読まれれば、どの点が自店のネットショップで不十分なのかが見えてきます。
広告についても、費用対効果の考え方が具体的に数値で目安が示されている点に好感が持てます。
これからネットショップを起ち上げられる方、ネットショップ運営で課題を抱えておられる方のおすすめの1冊です。
(1)店舗コンセプトがある店とない店の違い
無数のネットショップの中で存在感を発揮するには、競合点に見劣りしないアピールポイント(店舗コンセプト)を決め、わかりやすく伝える必要がある。
店舗コンセプトがあると、その店の何を見ても、その裏にあるコンセプトが伝わり、一貫性を感じる。
店舗コンセプトがないと、店舗運営に軸がなく、店の意図が伝わってこない。行き当たりばったり感が出る。
例えば
「どんな工具でも必ず見つかる品揃え」
「グルメコンテストで優勝したラーメン店」
「問屋直販だからできる激安価格」
など、店舗を一言で説明できるほど明確にしたい。
ラーメン店、ケーキ店、焼肉店などの実店舗では、メニューを増やしすぎて特徴がぼやけてしまい、新規顧客獲得が難しくなるケースがよくあります。
ネットショップでも、商品を増やしていく中で、コンセプトが曖昧だと、筆者の言われるように一貫性が薄れ、コンセプトがよくわからない店になってしまうことがあります。
店舗コンセプトはリアルでもネットでも大変重要なポイントです。
時々は店舗コンセプトを見なおした上で、取り扱い商品やデザインを見直すことが必要です。
(2)特集ページを作る意味
例えば楽器店でアクセス解析をみていると、特に工夫をしていない「入門用楽器」のカテゴリーページの訪問が多かったとしよう。
これは潜在的な需要がある証拠だ。
このように力を入れたいカテゴリがあった場合は、それを強化して「特集ページ」を作るといい。
特集ページとは、店舗からの提案として「1つのテーマで商品を揃えた」ページを指す。
実店舗で言えば、スーパーマーケットの一角の「北海道グルメフェア」のような店舗内イベントに近い。
メリットは、たくさん並べることによる下手な鉄砲効果や、掲げたテーマが魅力的であれば単体では売れない商品の露出強化ができることがある。
ファッション・インテリア・雑貨など、商品を選ぶ楽しみが重視されるような店はこの特集企画は特に重要。
・売れ筋商品を集める「いま当店で人気の商品を揃えました」
・用途に合わせた商品選定「パーティー必須アイテム特集」
・客層に合わせた提案「50代に人気の美容特集」
・商品カテゴリーに応じた特集「バイヤーイチ押しのシャンパン特集」
「検索よりも、この特集ページの中で探す方が楽だ。」
と思ってもらえれば、他店への流出を防ぐ効果も期待できる。
実店舗の百貨店や雑貨店の「○○フェア」といったものや、雑誌の「○○特集」などが切り口の参考になりますね。
いつも変わらない感じで商品が紹介されているよりも、このように特集で切り口が違うと顧客の目を引きます。
楽器店の例のように、特集を組むヒントを得る目的で、どのような検索キーワードで訪問されているかを注目するのは良い視点ですね。
検索キーワードから顧客のニーズを推測し、仮説を立てて実行する。
ホームページやブログのアクセスUPにも重要な視点です。
(3)BEAFの法則で縦長商品ページをつくる
オリジナル商品はかなり売りづらい。
購入率0%という商品も珍しくない。
ユーザーに「あえて」ネットで買ってもらうには「近所では買えない特別感」を演出する必要がある。
そこで必要になるのが、無名商品の魅力を語り、購入まで誘導する縦長商品ページだ。
商品ページのあるべき構成・適切な順番は「BEAF」で表現できる。
1.Benefit「どんな商品?」・・・購入メリット。商品利用シーンの描写、魅力的な写真など
2.Evidence「でも本当?」・・・論拠。マスコミ実績、ランキング、「お客様の声」の引用など
3.Advantage「似た商品もあるよね?」・・・競合優位性。品質、価格、利便性など世間の相場と比べてアピール
4.Feature「買っても大丈夫?」・・・さまざまな特徴。色、サイズ、賞味期限、内容量、素材、成分など
この4点の要約も必要。
実際に支援に関わるネットショップで、足りないなと感じたのが”商品利用シーンの描写”です。
単に商品写真だけが掲載されているケースがとてもよくあります。
物を売るのではなく、事(体験)を売るという視点で考えても、”商品利用シーンの描写”は外せないです。
お客様から利用しているシーンの画像をいただく。モデルを活用するなど、利用していることがイメージできる工夫をしたいです。
●正しいメールマガジンによる顧客フォロー3ステップ
メルマガは「狩猟」ではなく「農業」
1.種をまく・・・読者を増やす。開封される件名をつける
2.育てる・・・愛情を込め、押し付けすぎない程度に商品を案内しながら気長に
3.収穫する・・・メルマガの読者をメインターゲットに店舗内イベントを開催し、爆発的な売上を収穫する
信頼アップにつながる雑談(コンテンツ)
・注意の呼びかけ・・・よくあるトラブルと予防策など。アフターケアの充実を印象づける。
・賢い使い方・・・商品価値を向上させる。「誤解を解く」内容なら、プロらしさがさらに向上。
・風景の描写・・・店舗や生産地などの近況を報告する。親近感や本場感を演出。
・メルマガクーポンを備考欄にキーワードで入力してもらい、メルマガ読者限定特典をつける。
実店舗のお店でも、既存顧客をほったらかしにして、新規顧客開拓ばかりに取り組んでいると、
景気が悪化すると一気に業績が傾くケースがよくあります。
ネットショップでも顧客フォローは極めて重要です。
通販大手で買い物をしてみると、ニュースレター、DM、メールマガジンなど、いかに顧客フォローを重視しているかがわかります。
メルマガのフォローは狩猟ではなく、農業というのは名言です。
大切なお客様を1人1人積み上げていく感覚を持ちましょう。
【目次】
はじめに
本書の読み方
序章
第1章 空回りしないためのネットショップの基本の法則
第2章 商品タイプを踏まえた集客の法則
第3章 店舗コンセプトを活かした接客の法則
第4章 「長く売れる」ための追客の法則
第5章 成長段階別・運営実務の法則
【今回の一冊】
◆タイトル:『売れるネットショップ開業・運営』
◆著者:坂本悟史 川村トモエ
◆出版社:インプレスジャパン
◆ページ数:232ページ
◆2010.5.4
【おすすめ度】(5段階)
●総合 ☆☆☆☆
●読みやすさ ☆☆☆☆
【関連書籍のレビュー】
【関連ブログ】
ネットショップのUSP3条件『成功するネットショップ集客と運営の教科書』
●ネットショップ成功に第一に必要なもの~USPの3条件~
(1)オズボーンのチェックリスト
(2)ユニークさを見出す3つの段階
(3)商品の4パターン
●コミュニティを創るための5つのステップ
→開業前に店舗コンセプトを含む準備をしっかり考えたい場合はこちらの方がおすすめです。
【関連サイト】
【編集後記】
業務全般の見直しの結果、2017年からは本の紹介ブログは不定期とさせていただくことにしました。
本の紹介以上に、現場を通じて学んだことなどをブログで更新していく方針にします。
もちろん読書はずっと続けていますし、今後も「これは!」というものは紹介していきます。
同時にメールマガジンは2016年を持ちまして終了させていただきます。
長い間の購読ありがとうございました。
【目指せ300冊レビュー!】
今回で208目です。
【最新の書籍紹介はこちらで掲載しています】
【過去の書籍紹介はこちらのブログに書いていました】
【おわりに】
最後までお読みくださりありがとうございました。
今後とも引き続き、よろしくお願いいたします。










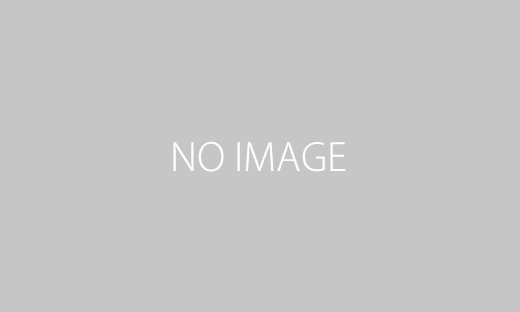
この記事へのコメントはありません。